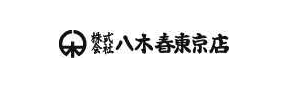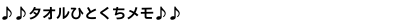

名入れタオルを配る風習は、江戸時代に歌舞伎役者がごひいきに配った名入れの手拭いが始まりといわれています。それを江戸の職人や商人が真似て自分のお客さんに差し上げるようになり、次々と華やかな物をつくっては粋を競い合ったそうです。
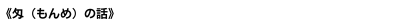
タオルの業界ではタオルの重量を表すのに尺貫法の「匁」という単位がいまだに使われています。
タオル1ダース当りの重量を匁(1匁は約3.75g)で表現します。単純にいえば、200匁のタオルは、1ダースで約750g(200×3.75)、1枚62.5gが一応の目安ということになります。
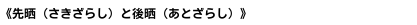
タオルは生産工程において、先晒と後晒とに分けられます。先晒は準備工程で糸を晒したりしてから織機にかけます。従って織りあがったタオルは一応完成品です。一方後晒は生糸(なまいと)のまま準備工程を通り織機に掛けられますので、織りあがったタオルはまだ半製品で、このあと晒(漂白)や染色工程を経て完成品となります。
しっかりとした手触りのジャカード織りは先晒が多く、やわらかな白タオルやカラータオルは後晒が多くなっています。

綿糸の太さは番手で表示されます。ただし直接的に太さを示すものではなく、糸の長さと重さの関係で表しています。世界各国で様々な表示方法がありますが、日本では標準重量を1ポンド(453.59g)とし、この長さが840ヤード(768m)の糸の番手を1番手としています。番手の数字は1ポンド当たりの糸の長さが840ヤードの何倍かを示すことになります。例えば20番手の糸は1ポンドの糸の長さが840×20=16,800ヤードとなります。従って、番手の数字が大きくなるほど糸は細くなります。
日本のタオルは20・30・40番手の糸が多く使われています。

参考資料
『タオルの知識』
『テリーちゃんのタオル講座』 東京タオル卸商業組合編
|